
まだまだやることは山ほどある。そういう意味ではこの人生で、いいんだなって思います。よかったっていうと終わっちゃうから(笑)。
スタイリストという職業が日本で知られていなかった60年代半ばから、広告やCM、音楽、映画など幅広いフィールドでスタイリングを手がけ、今なお最前線を走り続けている高橋靖子さん。T-レックスやデヴィッド・ボウイなど海外のスターのみならず、忌野清志郎、布袋寅泰、ももいろクローバーZなど日本の著名アーティストからの信頼も厚く、また、彼女の書くエッセイは貴重な時代の証言であるとともに、そのチャーミングな人柄が表れている語り口が、若い人たちも魅了しています。時代をともにした大御所のクリエイターたちのみならず、若い後進からも「ヤッコさん」の愛称で親しまれる彼女は、今年74歳という年齢を全く感じさせないほど元気いっぱいでキュート。働く女性の大先輩として、そのパワーの秘密を聞いてみました。
私が4歳のとき、戦争が終わりました。終戦のその日の情景をよく覚えてるんです。外は本当にカンカン照りで、家の中はほの暗くて、そこに近所の人や大人たちが一緒に座ってて、私は一番後ろで立っていた。ラジオから終戦を伝える玉音放送が流れたけど、言葉がちょっと特殊だから父以外の人は戦争がどうなったのかわからなかった。それでみんなボーッとしてたら、父だけが「戦争が終わった!」って外に飛び出していったんです。父は超ロマンチストで、その日のことをよく話してくれました。カンカン照りの中で道を歩いてたら、ヒマワリの花が咲いていて、その下で少年が絵を描いていたんですって。そのヒマワリの絵をもらって、父が1枚だけもっていたフジタ(藤田嗣治)のデッサンを、その少年が通っている学校に寄付したんです。
私は2歳ぐらいからの記憶があって、それはムービーじゃなくて1枚の絵や写真なんです。家が霞ヶ浦海軍航空隊のすぐ近くだったので、B29が群体できて爆弾をどんどん落とす、その音や火を覚えています。自分でもスゴイなって思うんだけど、みんなが死にそうな思いをしてる中で、当時2、3歳なのに「絶対に私は死なない!」と確信してました。空襲警報がないときは、ウチの防空壕の中に作ったブランコで遊んだりしてました。近所じゅうの人が集まるぐらい広かったので。戦中は霞ヶ浦海軍航空隊の御用写真館だったので、比較的豊かだったのでしょう。ひもじい思いをしたという記憶はありません。
戦後すぐに、PX(進駐軍が銀座の和光や松屋を接収し、米軍のための商業施設として活用)に勤めていた叔母が米兵と結婚しました。私が東京へ遊びに行くと、PXで買ったハーシーのチョコレートやカラフルなジェリービーンズをいっぱいお土産にもたせてくれるんです。あの頃のチョコレートってゴールドの紙箱にパッケージされていて、ウチのあたりではそんなものをもっている人なんていなかった。私はそのゴールドの紙箱に、お人形の服や折り紙で折ったものを入れてました。
叔母は超ハデで日本人離れしてましたからね。その影響かどうかわかりませんが、私は中学生ぐらいになると、アメリカのペンパルに手紙を書いたりもしてました。家の周りは田んぼや畑ばかりだったけど、都会的な文化やオシャレなものが好きで、自分だけは頑張ってそういうことをしてたんです。
当時は内職で服を作っている人に1年に1回作ってもらうという感じで、特にかわいいものを着せられたりはしませんでした。本や雑誌も全然買ってもらえなくて、本屋さんでずーっと『ひまわり』や『それいゆ』を立ち読みしてました。女学校に通っているお姉さんから、紙が茶色に変色してボロボロになった古い『ひまわり』や『それいゆ』をもらって、手芸のページを見てお人形を作ったり。そのお人形は、まだウチにありますよ。今でも撮影用の小物は自分で作るので、一生『ひまわり』『それいゆ』ですね(笑)。
高校生活はすごくつまらなかった。中学の成績は良かったんですけど、県立で第一ランクの元男子校を受けちゃダメだって親から言われていて、第二ランクの女子校に行ったんですが、校歌を歌うのもイヤだと思っていたくらい女ばっかり。それで、田舎だし、何も言うことを聞いてもらえないっていうのがすごくあったから、大学は東京へ行こうと決めていました。大学受験も親が反対して、高校3年の夏休みに「東大ならいい」って言われたけど、受験勉強が間に合わなくて早稲田の政治経済学部に入りました。法学部も受かって、そっちは女子が30何人いて、政経は4人しかいなかったので選んだんだけど、政経の男の子は政経の女の子を好きにならないから、ちょっと違ったなと(笑)。
大学4年のときに、久保田宣伝研究所(宣伝会議社の前身)のコピーライター養成講座に入ってコンテストで1位になったんです。それで電通のえらい人が声をかけてくださり、試験も受けずにあやふやに入社しました。化粧品や百貨店の仕事のために、女性のコピーライターが必要だったんです。配属された写真部と同じ建物にある広告代理店のライトパブリシティに、しょっちゅう遊びに行ってました。土屋耕一さん、篠山紀信さんなんかがいた時期ですね。電通では「10年頑張ったら部長にする」って言われていたんですけど、8カ月で辞めました。
原宿のセントラルアパートにあったデザイン事務所のレマンにコピーライターとして転職したんだけど、雑用をやらされているうちにいつの間にかスタイリストになって独立しちゃったの(笑)。セントラルアパートには鋤田正義さん、繰上和美さんをはじめカメラマンの事務所も多く入っていたので、彼らのところをまわっていると仕事がどんどん増えていきました。チラシから大きなCMまで、いろいろな仕事をしましたよ。まだスタイリストという職業が認められていなかったので、ギャラも最初は1500円くらい。リース料に含まれていたりして、ものすごく安かったんです。
 公私ともに仲の良かったモデルの山口小夜子さんと。日本のファッションカルチャーの黎明期を歩んだ2人のこの写真は70年代に撮影されたもの。撮影:染吾郎、写真提供:高橋靖子
公私ともに仲の良かったモデルの山口小夜子さんと。日本のファッションカルチャーの黎明期を歩んだ2人のこの写真は70年代に撮影されたもの。撮影:染吾郎、写真提供:高橋靖子
飛行機のチケット代がエコノミーでも往復で68万円くらいの時代です。滞在費も含めて、よく貯めましたよね。当時はみんなが「アメリカではこんなのが流行っていて〜」って、すぐアメリカの話をするので、そんなにレベルが高いのなら見ておこうと思って、広告代理店へ英文の手紙を書いて、トップスタイリストのアシスタントについたんです。その人が仕事以外でも「今日はここのホテルでランチしようね」とか、すごく面倒を見てくれたんですよ。
リチャード・アヴェドン(アメリカを代表するファッション写真家)のスタジオに行ったときは、彼は絶対スタッフ以外をスタジオ内に入れないんですが、ラッキーでした。当時彼のアシスタントをしていた坂田栄一郎さんが「僕はもうすぐ日本に帰るんだ」と言っていました。ちょうどメトロポリタン美術館で写真展「ポートレート」をやる前だったので、紙焼きの写真がたくさんありました。やっぱり当時の日本ではあり得ないオシャレなスタジオで、テーブルには果物やサンドイッチなどの食べ物がいっぱい並んでるんですよ。そういうのって素敵だなって思いましたね。
ニューヨークには6週間いたんですけど、結果的には、自分が思うようにやっていれば間違いないという確信がもてました。手の届かないところに何かがある、という思い込みから解放されたんです。
私が自腹でニューヨークへ行ったことを知った寛斎さんが、「自分のお金を使って行くんじゃなくて、仕事すればいいじゃない。俺のショーやれば?」って誘ってくれて。初めてのロンドンで大変なこともあったんですけど、何とかできちゃったんですね。
その次にロンドンへ行ったのは72年。鋤田さんから、「ヤッコさん、ロック好きだったらT-レックスって知ってる? 」って聞かれて「知ってる」って言ったんだけど、実は名前しか知らなかった(笑)。鋤田さんが彼らの写真を撮りたいということで一緒にロンドンへ行って、飛び込みでマネージャーに会ったらフォトセッションできることになったんです。そのあと、鋤田さんとT-レックスのフォトセッションがあったのですが、街のポスターを見て「変わった人がいるね」って二人で話してたら、それがデヴィッド・ボウイで(笑)。私が「連絡取ってみましょうよ」って言ってレコード会社に電話してコンタクトを取って、鋤田さんの写真を見せたら撮影OKになったんです。彼に着てもらった有名な寛斎さんの衣装も、服がグラムロックそのものだった。寛斎さんは最初、私がスタイリングしたことを知らなかったんだけど、自分の服をこんなふうに着る男がいるんだって驚いてました。
普段のボウイは、本当にエレガントで素敵。また、しゃべってるときの声がすごくいいんですよ。最初会ったときはシルクのブラウスを着てピアノの前にいて、まるで王子様だった。音楽系の仕事が多くなったのは、鋤田さんのおかげですね。私、ロックに詳しいと言われるけど、実は全然詳しくないんです。ただ、デヴィッド・ボウイやイギー・ポップとか、一緒に仕事をした人のことは詳しいですよ(笑)。
本当によく時間がありましたよね。離婚して20年になるけど、結婚・出産という当たり前のことを経験して本当に良かったし、何であんなに一人の男の人を愛せたんだろうと思うんですよね。息子も独立した今の孤独感って、本当に贅沢な孤独だと思っていて。もう少ししたら人生をまっとうするわけだけど、まだまだやることは山ほどある。そういう意味ではこの人生で、いいんだなって思います。よかったっていうと終わっちゃうから(笑)。
 スタイリストの先駆けとしてファッションシーンをリードしてきたヤッコさんは数多くの各界のカリスマたちと交流し続け、現在も変わらず第一線で活躍しています。写真は80年代に撮影されたもの。写真提供:高橋靖子
スタイリストの先駆けとしてファッションシーンをリードしてきたヤッコさんは数多くの各界のカリスマたちと交流し続け、現在も変わらず第一線で活躍しています。写真は80年代に撮影されたもの。写真提供:高橋靖子
人と巡り会うことじゃないかしら。一人でいるのが贅沢な孤独だって言ってるけど、人が大好きだから。この夏くらいから、1日も一人でボーッとしていたことがないんですよ。毎日、誰かと会う用事が入っちゃう。そうじゃなくても、時間があると新宿の伊勢丹に行ってあれこれ見てるし、青山だと紀ノ国屋、成城石井、ピーコックで食品を買ったり。仕事もずっと一人で全部やっていて、会社を作ろうと思ったことも1回もないんです。スタイリングに必要なものはぜんぶ自分で見て探す。もちろん、その時代ごとに一人ずつアシスタントはいましたけどね。
ヨガを45年ぐらい前からやってます。私、朝日カルチャーセンターの第一期生の生徒なんですよ。その頃は高名なヨガの先生がいて、健康食についても教えてくれました。ちゃんとした手作りのお醤油の味も教えてもらって、こういうものって本当に美味しいんだなってわかりました。質のいいお肉を仕入れているデパ地下の情報も調べました。でも本当はそれだけじゃダメで、ときどきジャンクなものも取り入れなきゃいけないって、社食の定食みたいなものもガツガツ食べるんです。そういうことを教わってから、食事には気をつけてます。今は朝をちゃんと食べることが大事かな。そのおかげかどうかわからないけど、体調を崩したことはないです。健康診断も毎年受けてますが、引っ掛かったことが1回もない。この間、初めて脳のMRIを撮りましたが、大丈夫でした。
絶対、それはあると思います。離婚したとき、体重が8キロくらい減っちゃったんですよ。そのとき、自分で言うのも何だけど、すごくキレイになっちゃって(笑)。それまでは髪の毛も長かったんだけど、ヘア&メイクの夢実人さんが「ヤッコ、これからは顔を全部出すこと!」と言ってバッサリ切ってくれて、それでこの髪型になったんです。
離婚した後、元気になったら他のことをしようと思って、ギターを買ったんです。それで新宿の雑居ビルにある知り合いのバーで、「流しに来ました!」って1、2曲歌ったことがあって。そこのママが「次もやっていいよ」って言ってくれて、今度は30分くらい8曲ほど歌いました。お客さんは20~30人かなって思ってたんですけど、当日になったら100人来てしまったので、2回制にして。外階段にはいろんな人からの花がびっしり並んで、すごい気晴らしになりましたね。困難なときにはバカ騒ぎするとか、違う方法で乗り切る。心の中では真面目に考えているんだけど、表現するときにダサイのはヤじゃない?ちょっとクレイジーなくらい騒いだほうがいい。
父の介護のことを書いた『家族の回転扉』で第19回読売ヒューマン・ドキュメンタリー大賞を受賞したときは、原宿のクエストホールで受賞パーティのコンサートをやったんです。私の他に川村かおりちゃん、西田ひかるちゃんなどのゲストも歌ってくれて、もう、どんちゃん騒ぎ(笑)。私は最初は着物を着て、それを脱いで自分でデザインした衣装に着替えたりして。
服で気持ちも変わるから、それは大事ですよね。でも私、高級志向がないから、良いものを長く着るというんじゃないんです。でも若者の服をそのまま着てたらバカみたいだから、逆に難しいんです。体型も変わってくるし。自分なりの工夫が必要ですね。
前はノートに毎日のように書いていたんですけど、今はフェイスブックに書くようにしています。事務所もないしマネージャーもいないので、「私はここにいますよ」ということを自分で発信する。みんなが負担なく読めるように、キュートなことを書く。やっぱり書くことは、練習しないとダメだと思いますし、リズム感が大事だと思っているので、一度書いたものも読み直して校正を重ねる。一番新しい『時をかけるヤッコさん』を読んでいただいた昔からの知り合いの編集者から「今までの本でベスト。自分の文体を確立したね」という手紙をもらって、それをウチの冷蔵庫に貼ってあります。同じことを自分で思っていたので、強い念は伝わったなって。
彼に「続けて書くように」と言われて、それは私にとって神の言葉みたいなものだから、これからは小さい頃からの記憶にある戦争のことを書こうと思っています。アーティストなどとの付き合いよりも、自分の中に向かって見つめることも必要な時期になったんでしょうね。もう一つは女性のセックスについてがテーマです。自分の心が深く傷ついたときに、どうやって女性として自分の中の性を取り戻していったか。そういう話を書いている人はまだ誰もいないんです。何年も前に、その話の最後だけは書いたんだけど、ちょっとずつリズム感を失わないようにして、完成させたいと思っています。(文=藤野ともね 写真=松井康一郎)

小雨が降る週末。取材場所のカフェでお会いした瞬間、周囲がパッと明るい雰囲気になるようなオーラを放つヤッコさん。エネルギッシュでチャーミングな人柄に多くの人が魅了されています。
撮影協力:SW11Kitchen 東京都渋谷区神宮前4-26-27ルシード神宮前3F TEL.03-6804-1456
1941年茨城県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、電通勤務を経て、原宿セントラルアパートにあった広告制作会社へ入社。コピーライターとして働きつつ、1960年代にフリーランスのスタイリストに転身。1971年単身ロンドンに渡り、山本寛斎のファッションショーを成功させる。その後、ジギー・スターダスト期のデヴィッド・ボウイの衣装を担当。また、鋤田正義によるデヴィッド・ボウイ、T・レックスのフォトセッションをサポートした。日本のスタイリストの草分け的存在で、現在もCMや広告など第一線のスタイリストとして精力的に活動し、多くのクリエイターに影響を与え続けている。1960年代から原宿、表参道を見つめ続けてきた語り部でもあり、著作も多い。エッセイ『家族の回転扉』は第19回読売「ヒューマン・ドキュメンタリー」大賞を受賞。
●高橋靖子の人生を知る三冊

60年代半ば、コピーライターとして広告業界に入ったヤッコさんは撮影の現場を手伝ううちにスタイリストになり、持ち前のガッツとセンスでキャリアを重ねていく。伊丹十三、山口小夜子、ユージン・スミス、寺山修司、デヴィッド・ボウイなどとの出会いを通して、現在に通じるさまざまなカルチャーが生まれた伝説の現場に立ち会ってきた、時代の証言としても貴重な一冊。イキイキとした文体で描かれる、何かをつかみたいと行動する20代の女性の青春物語。(河出文庫)
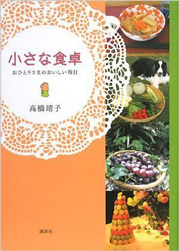
ヤッコさんの元気の源は食べることが好き!というところにもある。四季の移り変わりに敏感で、新しい情報には目がなくて、手を動かすのも好き。お茶や和菓子は心の栄養になるから、必要経費。テーブルセッティングだって自分流に。そんなヤッコさん流の食事を楽しむアイディアがいっぱい。家族のためにとかお客様を招くのではなく、誰も見ていない自分一人の食卓だからこそ手抜きをしない。楽しく読んでいるうちに、いつしか背筋がピンと伸びてくるような本。(講談社)

70年代初頭にデヴィッド・ボウイが山本寛斎のコスチュームを身につけていなかったら、あれだけのアーティストになっていただろうか? 世界を震撼させた強烈なイメージの仕掛け人であるヤッコさんの、ミュージシャンやアーティストとの交遊録。憧れの宇野千代とのエピソードに絡めて自身の離婚や介護も書かれており、パワフルなだけでない人生の影を知ることができる。T-レックス、忌野清志郎、布袋寅泰など、登場する面々の貴重な写真も満載。(文藝春秋)

