
「30代になってから、自分の心の声だけで動くということができるようになりました」
数々のショーや広告などに登場し、トップモデルとして活躍するアンジェラさん。ヨガの世界に精通し、過去には末期ガンを克服した経験を持ち、“美しく生きる”ということのお手本を示してくれるようなその凛とした姿勢は、多くの女性たちの憧れ。会話をしていると、クールでエキゾチックな容姿だけでなく、強さ、知性、芸術への探求心といった様々な要素が、人としての魅力を倍増させていることも伝わってきます。現在はモデルのみならず、海外誌のライターや、現代アートのギャラリーで展覧会を運営するなど、幅広い分野で活動の裾野を広げていて、その感性を磨き続けているアンジェラさん。14歳から始めた仕事の話、闘病の時期に思ったことなど、これまでの人生の片鱗を語っていただきました。
1歳半上の兄とすごく仲が良くて、いつも兄や兄の友達と遊んでいました。小学校に入る前までは、外で男の子と遊んでることが多かったですね。母ともとても仲が良くて、母と一緒にいた時間も多かったと思います。母は絵を描く人で、毎日スケッチをしたり墨絵を描いたりしていて、それをそばで見ているのが大好きでした。子供の頃に住んでいた家はちょっと大きい家で畑もあって、母は自分で野菜を育てたり、畑の案山子も自分で作ったりしていました。その案山子と私と兄が登場する物語の紙芝居を作って、よく寝る前に読んでくれたのを覚えています。(編集部注※アンジェラさんのお兄様は元モデルのユアンさん)
そうなんです。だから幼稚園に入る前の生活が一番楽しかったかもしれない。その頃のことを思い出すと、本当にユートピアのようでした。幼稚園や小学校も面白かったけど、とにかく家に帰るのが楽しかった。
友達を作らないといけないかなって思い始めたのは7~8歳の時ですね。その頃、母が乳ガンになって入院して、初めて母と離れて過ごす時間を経験して、なんとなく友達とか作らないといけないかなあって思って。母はその後元気になるんですが、私が10歳の時にガンが再発して、12歳の時に亡くなりました。だから10歳くらいから掃除や洗濯、ご飯の支度とか、家のことは全部やっていました。
はい。その頃は、家の外でも何かをやりたいと思っていたのと、ちょうどハーフのモデルが流行り始めてて、街でスカウトをされることが多かったんです。兄がちょっと前にモデルを始めてて、ある日、「今日も声をかけられたよ」って、もらった名刺を見せたら、「そこ、すごくいい事務所だよ」って薦めてくれて、それで会いに行ったらすぐ採用になりました。最初は年に一回か二回、お小遣いになるくらいな感じでできたらいいなって思ってたんですが、実際は、放課後毎日みたいなペースになってしまいました(笑)。
最初はファッションのことなんか全然知らなくて、雑誌もあまり見たことがなかった。それで面接の時に「どんな仕事をしたい?」って聞かれて、すぐ本屋さんに行って、勉強するようになりました。雑誌の中のどんなページがいいか、さらにその中から自分はどういう写真が好きなのかとか考えるようになって、カメラマンのクレジットも見たりするようになって。あと、神保町の本屋さんとかに入り浸ってファッションの歴史を勉強したり。その学んでいくプロセスが楽しかったですね。
父がアカデミックな人で、医学書の翻訳や、大学病院で医学英語を教えるなどの仕事をしていて、私も勉強もしっかりやらないとって思っていて、母親が亡くなった後、勉強に没頭したら、なんかすごくできちゃったんですよね(笑)。それでファッションの仕事をやっていくのか、ケンブリッジとかオックスフォードみたいな大学に行くのか、選ばないといけない時期になって、いろいろ考えたんですが、やっぱり仕事は辞めたくなかった。15歳から一人暮らしも始めていて、その生活も手放したくなくて、それでICU(国際基督教大学)に行くことにしたんです。
私、幼稚園の1年間と小学校3年を飛び級したんです。インターナショナルスクールだから飛び級ができて、だから16歳でハイスクールを卒業して大学に入学したんです。
普通はインターナショナルスクールからだと大検を受けないとならない。でも大検は18歳からしか受けられない。それで選択肢がICUか上智大学か聖心女子大学しかなくて、それでICUを選びました。でも、モデルをやりながら、もっと世界を広げたいと思って進学したんですが、授業はほとんどテストと就職向けというところに失望して、結局2年半でやめてしまいました。
その頃はモデルの仕事をしていても、自分のインターナショナルな部分や意識の深さを、どう活用していけるのかとか、常に考えて葛藤していましたね。10歳の頃から家のこともやって、中学から高校まで成績はほぼオール5。とにかく何でもしっかりやってきたけど、10代の頃は頭だけの知識とクリエイティブな部分と身体的経験のバランスが整ってなかった。でも、21歳の時にロンドンに引っ越してヨガの先生と出会って、そこでメンタルな部分と身体と感覚とのバランスがとれるようになってきたんです。ヨガとの出会いは本当に大きかった。人間として成長するために必要なものでした。

その時に付き合ってた人と大きな別れがあって、全部を変えたくなったんです。ロンドンは祖母が住んでるし、子どもの頃から毎年夏に訪れている場所だから、計画もせず身軽に行ける場所だったので。それで、それまで自分の中で消化しきれてなかった母の死とか、大きな別れの消化の仕方とかがわからなかったんですけど、ヨガの先生との出会いで、「自分一人で立ってないといけない」ってずっと走って来た私を受け止めてくれるスペースが見つかった。久しぶりに安心できる場所にいる自分を感じられて、問題を自分でどう消化していけばいいかという術も与えてもらいました。
『STORM』っていう事務所なんですが、どうせやるなら上を目指したいし、もしそこに入れなかったらもうモデルじゃなくてもいいかな、とりあえずアルバイトでもしようかなと思ってました。そうしたら入れてもらえることになって、すぐにGAPのインターナショナルのキャンペーンモデルが決まったんです。日本のシステムと全然違うので、毎日オーディションを受けに行ったり大変でしたが、でもその分、『イタリアン·ヴォーグ』のファッションエディターや、写真家のエレン・ヴォン・アンワースとか、ずっと憧れてきたすごい人たちと一緒に仕事ができて、それは本当に素晴らしかった。ただ同時に、常に自分の中で葛藤もあったんです。目指していた場所に到達すれば、それはプライドになるけど、到達すると、思っていたことと違うってことも多いじゃないですか。で、自分の価値観における本当の目標って何なんだろうって、ずっと考えていました。
25歳の時にインドに一人で三ヵ月間行って、それが素晴らしい旅だった。家族の中、あるいは社会の中のこのポジションとしての自分とか、そういったものが全部取っ払われて、まるで幼稚園前の自分に戻ったかのような自由さです。しかもインドっていう混沌とした環境の中にいたので、自分も混沌でいい。自分が何であってもいいと思えた。社会の中で機能する以前の大事な自分。なんとなく潜在的にはわかっていたけど、それがリアルに実感できて、自分を信じられるようになったんです。その後も、ヨガのワークショップとかでギリシャやメキシコ、イスラエルなど、いろいろなところに行きましたが、最初のインドは私にとって一番の旅になりましたね。
3か月ずっと自由で、毎日いろんなことを感じる日々。そこから毎日オーディションみたいな生活にはやっぱり戻りたくなくて、1年半くらいはヨガのワークショップをメインにやって、時々モデルをしてお金を作ってっていう生活をしていました。そうしたらガンが発覚して……。
ずっとリンパ球が硬くてゴリゴリしてて何カ月もなくならなくて、検査してもなかなか答えがでない。ちょうどギリシャを旅していた時に、祖母の危篤の知らせがあってロンドンに戻って、その時に再度検査をしたら、「末期ガンなので、すぐに治療しましょう」って言われて。あまりにも唐突だったので、とりあえず「1週間考えさせてください」って言ったら、「1週間も考えたらもう治療する意味がないかも」って言われて、「だったらなおさら1週間考えさせて!」って。
それで1週間ロンドンから離れて、田舎に住んでる友人の家に泊まらせてもらって。ホリスティックなことに詳しい友人で、そこで治療についていろいろ調べたり……、というか自分との対話ですね。自分はどうしたいのか。なんか意外な展開だったんで、「今、これが来るのか~」って感じでしたが、そのまま突っ走って治療に入っちゃうのがすごくイヤだったんです。母が自然体の人だったので、子供の時からあまり薬を飲まされてなかったし、ヨガもやってて、アルコールもほとんど飲んでなくて、何年かはお肉も食べてなかった。だから余計に、大量の薬を身体に入れることにすごく抵抗があった。でも、いろいろ考えて、やはり治療を受けようという気持ちになりました。
もしかして死ぬかもって考えた時に、兄のことが頭に浮かんだんです。私たち2人、幼い頃に母親を亡くしています。もし私が戻らない人になったら、兄がどうなるかって思って。それはダメだ、自分ができる最善のことをしないといけないって思ったんです。言葉にするのは難しいんですが、兄のことを自分のことのように思ってるから、兄のためにというより自分のために、ですね。彼が悲しい思いをするのを想像するだけでもつらかった。で、やるならば、「これは毒なんだ」っていう気持ちを排除して、「光を身体に取り入れる」っていうポジティブな気持ちになろうって、その日からもう迷わず、抗ガン治療を始めました。同時に自分でスーパーフードとかを取り入れたり、オゾン治療なども並行してやりました。
抗ガン治療で髪の毛がどんどん抜けていくから、髪の毛を洗う時とか触る時とか、すごく気を使ってそっとそっと触るようになっていくと、気持ちも弱くなっていく感じがしたんです。それで友人に連絡して「30分以内にバリカン持ってすぐ来て!」って(笑)、友達に坊主頭にしてもらいました。冬だったから超寒かったけど、それはそれで楽しかった。洋服の感じとかも変わるし、小さい時にロンドンでパンクスのお兄ちゃんとかを見て憧れてたから、そういう楽しみ方もしていました。でも段々そんなこと言ってられないくらいツライ時期が始まって。もうとにかく気持ち悪い。眠ることもできない。違う次元の苦しみですね。ずっと暗いトンネルの中にいるみたいな日々でした。
絶対治るという可能性しか自分の中に持てない。1%でも迷いがあったらヤバイと思ってました。だから病気のことは、本当に数人の友人にしか伝えてなかった。仲がいい友人でも、もしかしたらネガティブに考えちゃうかもって思うような人には言わなかった。もしかしたら治らないかもって思う人が1人でもいたらダメだと思ったんです。エネルギーってそういうものだと思うし、そのくらいギリギリのところにいたんだと思う。
治療は半年間続きました。その時は、とにかく生きるということに集中して、それから再検査があって、治療は終わったんですが、その後1年くらいは、まだすごい量の薬が身体に入っているから、その頃のほうが身体も頭も心も、どんよりとしていました。それで、ヨガをちょっとずつゆっくりやって、1年くらいかかって、やっと抜け出した感じですね。

はい、兄にも会いたかったし、ちょっと日本に長く帰ろうかなと思って。その頃、兄が洋服屋さんをやってて、それを手伝ってって言われて、兄や兄の友人と過ごす時間が多くなっていくんですが、友人たちと一緒に日々が楽しく過ぎていくっていいなあって思ったんですよね。ものすごく優しくて温かい感じがして、そういう感覚が久しぶりだったんです。それは母が亡くなって家族から独立して以来の感覚でした。自分一人で頑張らないといけないっていう状態から抜け出せた。それで兄の会社で国際PRの仕事をさせてもらったりして、社会の風にあたる心の準備がまだできてなかった時期に、いい環境で過ごせたんです。そうこうしていたら、「アンジェラ、帰って来てるなら撮影させてよ」って声をかけてくださる方々がいて、モデルの仕事をやるかどうか、ちゃんと決めないといけないなあと思うようになって。それが日本に帰って来て2年目くらいでした。
海外だとモデルは洋服を見せる人、ファッションを提案する人に限られてしまう。でも、自分がモデルをやることで何かを人に伝えられる立場になれないだろうかって考えた時に、日本だったらその可能性があると感じました。アンジェラっていうパブリックパーソンとして、世の中との関係性を深めていくことをまだ完全にできていないと思って、それでもう一度ちゃんとモデルをやってみよう思ったんです。事務所に入り、モデルの仕事だけじゃなく、TEDトークでスピーチをしたり、ライターとして雑誌で記事を書いたり、そういう方向に動き始めました。それが31歳くらいの時ですね。
やったことのないことを仕事としてやらせてもらうってすごいことなんですよね。自分は人前で話せるし、文章も書けるって思ってても、証明するものがないじゃないですか。でも、今のモデル事務所の社長がサポートしてくれて、いろいろな道が開けてきた。自分のことを書いたりするだけじゃなく、海外の雑誌でインタビューをして原稿を書くという仕事も増えていきました。アーティストや建築家、デザイナー、文化人とかをインタビューするプロセスでの頭の使い方もすごく面白いと思って、考え方もワイドになってきた。
すると美術館やギャラリーで作品を観た時なんかも、きれいな色だなあとかだけじゃなく、そのプロセスを考えたり、仕事っていうつながりで一歩踏み込んだ関係性が持てるようになってくるんです。インタビューをするとなると、作家や作品のことを自分の言葉で書かないといけない。となると、かなり深い理解が必要になる。過去の作品をリサーチして、その裏にあるその人のことをもっと知らないと、インタビューにたどりつけない。そういう勉強をするプロセスを、自分はもともとすごく好きだったってことを思い出しました。
はい。30代になってからは、頭じゃなくて、自分の心の声だけで動くということができるようになりました。母親を早く亡くしているので、私は常に母性を求めいて、自分の中の母性が子供である自分を抱えて生きているような感じがずっとあったんです。自分の中で自分が子供になったり大人になったりって、その繰り返しがツライと思うこともあった。でもヨガを続けていて、やっとそれが自然にできるようになりました。コントロールというか、温度調整のような感じ。そうやって自分との向き合い方が上手にできるようになると、他人との付き合い方にも無理がなくなってくるんです。

以前からアートは好きでしたが、『SCAI THE BATHHOUSE』は、観た展覧会がどれも素晴らしくて、そのバランスが自分に合ってると思ったんです。アーティストの選び方にしても、エモーショナルなんだけど、ウェット過ぎずドライ過ぎず、そのバランスがすごくいいなと。
毎回SCAIのオープニングに行って、キュレーターの方とかにいろいろ教えていただいてりして、最初は何も感じなくても、バックグランドを知ると、いきなりその作品が自分にとってパーソナルなものになったりする。それまでどうでもよかった、ニュートラルっていうより、むしろ関係ないって思ってたことが、ふとした言葉でとても近いものになる。そのエネルギーの転換が素晴らしいと思って、そのつなぎ目としての仕事に、だんだん興味を持つようになってきて、それで具体的に何かをやりたいって思うようになりました。
タイのアーティストのアピチャッポン・ウィーラセタクンの展覧会に来た時に、映像作品を何度も何度も見て、閉館時間近くになっても、その部屋にずっと座ってて、終わってからスタッフに、バイトでもいいから何かしたいって言ったんです。でも冗談にしか思われてなくて(笑)。それでオーナーの白石さんにも直接、「通訳でもアルバイトでも何でもいいので、レギュラーに関係性を持ちたい。もっと勉強したいので、私にできることがあれば声をかけてください」って言ったんですけど、やっぱりあんまり信じてくれていないようで(笑)、でも何度も念を押したら、「いろいろやってもらえることはあるよ」っておっしゃってくださって、それでミーティングをさせてもらって、やってみようかってことになったんです。
最初はお互いにトライアルですよね。私もどれだけできるかわからないし。英語はできるし知り合いのコレクターとかはいるけど、美術の勉強もちゃんとしてないから、勉強させてもらいながら仕事もさせてもらうって感じなんですけど、チームの皆さんが本当に温かく迎えてくださって。今はもう1年半経ちましたけど、単身で海外出張に行かせてもらったり、すごく刺激的な毎日です。誰に会っても一流の人のアドバイスってみんな一緒で、「とにかくアートをいっぱい見なさい」って言われる。だから、とにかくいろいろ展覧会をまわったりしていて、毎日が勉強。ゼロから始まって、今はさまに一歩ずつ進んでいるところですね。
そうなんです。SCAIの作家で最初にドーンと心に入ってきたのがダレン・アーモンドでした。彼の祖母がテーマとなっているインスタレーションを見た時に、いきなり涙が出てきた。具体的に何がどうだっていうんじゃなくて、ただただ、すごいエネルギーを感じたんです。アーティストトークにも行って、すごい衝撃を受けて。本当に素晴らしい大好きな作家さんで、展覧会までのプロセスも夢のようでした。機材のチェック、作品の展示、インビテーションのデザイン、作家の滞在のアテンドとか、すべてのプロセスに関わると、展覧会の全体像も見えてくるので、とても実りある経験になりました。
こういうふうにアクティブにいろいろな仕事をしてて、頭の使い方とか体の使い方とかワークアウトの仕方とかが、自分らしく展開していってる感じがします。モデルも、文章を書くことも、アートの仕事も、すべてがフィードバックし合っていくんですよね。だから、モデルに対しての考え方とかも変わってきました。もちろん洋服の見せ方だったり、洋服の表情の遊び方だったりという基本はありますが、それが筋肉だとしたら、スピリッツの部分は、ちゃんと自分に忠実に生きているかどうかってことなんじゃないかと思うんです。モデルって、こういう生き方をしてますって身体で表現する部分もあるじゃないですか。20代と30代では求められるものも違うし、表現できるものも違うけど、私にとってのモデルって、こういうことなんだっていうことがわかってきて、より大事なことに集中できるようになってきました。ホント日々勉強。でもすごく楽しくて、今はもう毎日が幸せです。
今はモデルの仕事を優先していますが、基本、週三日出勤しています。モデル事務所の社長も、私が人間的に成長することが一番大切だって、このこともサポートしてくれて、本当に周囲の方たちの優しさのおかげで、この幸せな生活がある。自分がやりたいと思うこと、やってみて面白いこと、上手くできることってちょっとずつ違う。でもやってみるしかない。そうやってやっとここにたどり着けたって感じで、今はただクビにならないことを願ってます(笑)。
(文=freesia編集部、写真=松井康一郎、ヘアメイク=森田佳奈(Van Council))

取材はアンジェラさんの仕事場でもある『SCAI THE BATHHOUSE』で行いました。上野·谷中エリアにあるこの現代美術のギャラリーは、200年の歴史を持つ銭湯「柏湯」を改装し1993年にオープン。瓦屋根に煙突がそびえる外観とは裏腹に、中はモルタルの床+白壁のニュートラルな展示空間。日本のアーティストを世界に向けて発信すると同時に、日本ではまだ紹介されていない海外の優れた作家を積極的に紹介しています。●『SCAI THE BATHHOUSE』東京都台東区谷中6丁目1-23 Tel. 03-3821-1144 http://www.scaithebathhouse.com/
1978年東京生まれ。14歳の時に雑誌『Olive』でモデルデビュー。『SPUR』『流行通信』『High Fashion』などのモード誌やショー、CMなどで活動後、1999年に渡英。その後ロンドンを拠点にNYやパリでも活躍。欧米の一流ファッション誌を始め、海外のクリエイターとのコラボレーションなどで多くの作品に携わる。ガン闘病を経て、2006年に日本に拠点を移してからは、モデル業をメインに、トークショーや執筆、デザインなど様々なスタイルで活動を続け、2011年には自らデザインするジュエリーライン『Angela for Patrick Cox』をローンチ。2013年に『TEDxSapporo』にてトーク。2014年からは『SCAI THE BATHHOUSE』でアート関係の仕事にも携わっている。旅と音楽、ワインとヨガをこよなく愛する。
●アンジェラがお薦めするアートな三作品
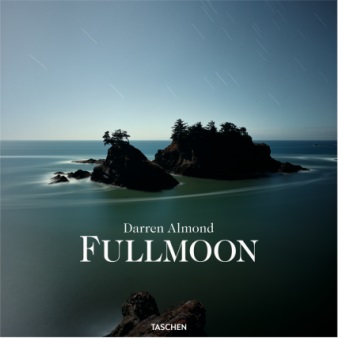
1997年に英国の現代美術界に旋風を巻き起こした「センセーション」展に最年少で参加し注目を集めて以来、同国を代表するアーティストの一人として活躍するダレン・アーモンドの作品集。本作は満月の光だけで浮き上がってくる幻想的な風景を世界各地で撮影したシリーズ。時間、記憶、旅などをテーマとする彼の作品は、写真から立体、映像まで多岐にわたり、いずれも抒情的かつ幻想的な美しさで観る者の胸を打つ。(Taschen)

アピチャッポン·ウィーラセクタン監督作、2010年カンヌ国際映画祭パルムドール賞受賞のタイ映画。死期を悟った老人ブンミさんが静かな余生を送っていると、亡くなった妻の霊や猿の精霊になった息子が現れる。人間社会と異界が地続きになっていて、さらにブンミさんの前世の記憶も描かれるという、ファンタジーを超えた独特の世界観に圧倒される。受賞直後の監督の「タイの幽霊・精霊たちに感謝したい」というチャーミングなコメントも話題となった。(DVD:角川書店)
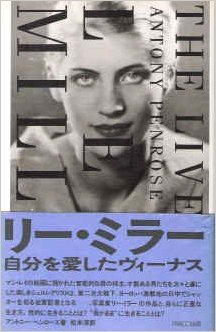
1920年代にニューヨークでモデルとして活躍。その後は写真家としてポートレイトや、第二次世界大戦中は『Vogue』公式の戦場写真ジャーナリストとしてドキュメンタリーの分野でも活躍したリー・ミラーの伝記。ピカソやジャン・コクトーなど多くのアーティストと交流を持ち、マン・レイのモデル兼恋人だったことでも知られ、戦後は料理研究家となる彼女の数奇な人生が、ドラマチックに語られる。日本語版は『リー・ミラー 自分を愛したヴィーナス』(PARCO出版)

