
「自分の一番いい状態とはどういう状態か、まずそれを知るのが大事なんです」
マドンナのプライベートシェフを10年近く務めたことで知られる西邨マユミさん。マクロビオティックの食事は、第一線で長く活躍し続ける多くのセレブやアーティストが実践していることでも知られていますが、西邨さんのレシピが、マドンナのあの年齢を超えた完璧な肢体や驚異的な精神力を支えていたのです。玄米菜食と東洋の陰陽思想を取り入れた食事法を基本とする、自然との共生を謳う一つのライフスタイルともいえるマクロビオティック。その考えをより多くの人に伝えたいと、 現在は“包丁を抱いた渡り鳥”と自称するほど、常に世界各地を飛び回っている西邨さん。今回、ベルリンの日本食レストランULAでワークショップを行っている最中にお会いする機会を得て、そのダイナミックな人生、マドンナとの時間、食に対する想いなどをじっくり語っていただきました。
篠島にある旅館の四女として生まれました。祖父母が開いた小さい旅館ですけど、お庭があって、お掃除を任されたり、小さな頃から家のお手伝いをするのは当たり前でした。海岸から砂が飛んでくるんですが、砂を一つもないくらいきれいにしないと祖母に怒られるんです。小さい庭ですが、子供からすると宇宙くらいの大きさ。拾っても拾って松の葉がなくならないみたいな体験を、子供の頃からしていました。
篠島はお魚のお造りとか、春はハモ、冬はふぐが獲れるところなので、てっちりなどが有名です。愛知県には人が住んでいる島が3島あるんですが、この2月に島を振興するイベントで声をかけられて、メニューを作って、お話もさせていただきました。(*現在も旅館はご家族が続けられています。篠島観光ホテル大角http://shinojima-oosumi.com/)
そうですね。でも実家にいる時はそういうふうには感じなかったです。姉たちはきれいに着飾ってお客様の接客をして、私はキッチンでまかないの準備や食器洗い。ここにいたら絶対に自分には日は当たらないと思っていました(笑)。11歳年上の兄が料理をしていたので、料理人になればいいかもとは思っていました。
短大の時に、今も活動している“センチメンタル・シティロマンス”というバンドに出会いました。それを見て「ひゃー、ステキー!」みたいになっちゃって、その後、バンドまわりのお手伝いをしたり。でも、週末はちゃんと実家に帰って旅館のお手伝いをしていました。その頃に出会った人たちの中に、私の子供の父親になった元旦那(以下“西邨”)がいるんですが、彼を通していろいろな本に出会いました。
ボストンの女性たちが集まって女性について考えた『Our Bodies, Ourselves』や桜沢如一の『新食養用法』、『東洋医学の哲学』、ルドルフ·シュタイナーなども読みました。現在は“OSHO”として親しまれているバグワン・シュリ·ラジニーシなどにも感化されていますので、そういう意味ではヒッピーかもしれませんね。ベジタリズムは直感的に体にいいことなんじゃないかと思っていました。
20歳くらいでボーイフレンドができて、将来、子供を育てるかも、ということを考えた時に、アレルギーがあることが気になり始めたんです。以前は実家できちんと食事をしていたけど、街に出て食生活が変わって、甘いお菓子や飲み物なんかも増えていたわけです。高校3年生くらいからアレルギーがひどくなっていって、短大の頃になんとかしたい、食生活を変えたいと思っていた。それでマクロビオティックの本が一番しっくりきました。世界平和、自分たちの健康、それを一気に解決できる方法だと思いました。
5年くらい実家を手伝って、行ったのは25歳の時です。桜沢如一先生のマクロビオティックをもう始めていて、たまたま名古屋の知り合いが、ボストンに『マクロビオティック健康法』っていう本を出している久司道夫さんという方がいるよ、と教えてくださった。読んだら素晴らしいので、この先生から教わりたいと思ったんです。その時、既に入籍していた西邨がボストンに住んでいたので、一石二鳥じゃないかということで、ボストン行きを決めました。これは私の使命。This is itと思ったわけです。

まずボストン大学の外国人向けの英語クラスに入りました。80年代っていい時代だったんです。英語の学校に籍を置けば、ビザが5年取れました。それで3年で何とか語学をマスターし、2年でマクロビオティックを習得しようと思ったんです。でも、実際は学費も生活費も高くて、あっという間に貯金がなくなりそうになって、「クシ インスティティュート」に行く余裕もない。(※「クシ インスティティュート」は、久司道夫が主宰するマクロビオティックの教育や普及を行なう施設。世界各地にあり、ここで研修を受けた学生数千人が各国で自然食やオーガニック運動、代替医療などの分野で活躍しています)
その時に、お料理をする書生として、私を久司先生に紹介してくれた方がいて、久司先生からお電話があり「うちに来ませんか?」とお誘いを受けたんです。でも、「先生、すみません。私、まだマクロビオティックを勉強していないので、お料理できるかわからないんです」と言ったところ、「あなた、日本人でしょ」「はい、そうです」「じゃあ、大丈夫よ、できるからいらっしゃい」と言われて。そこで図々しく、「お手伝いをしながら、学校にタダで行かせてもらうのはありですか?」って聞いてみたら、「オッケーです」との返事。それで、マクロビの学校に通わせてもらいました。それも夫婦2人で、ですよ。
そうです。本当に書生。西邨は先生をあちこち連れていく時に運転をする。私はもっぱらお料理をする。門前の小僧じゃないけれど、先生がどういうことをされているかを見るのが一番勉強になりました。英語はまだできませんでしたが、お料理のクラスは見ればわかるので、お料理だけは失敗もたくさんありましたけれど、いろいろ教えていただいて、1年後に先生がマサチューセッツ州の山に土地を買われて、「クシ インスティティュート」を将来移転したいということになったので、私たち夫婦も一緒に行くことにしました。
全然違いましたね。まず、アメリカは穀物の種類が豊富。日本ではその頃はまだ、今のようにいろいろな雑穀は販売されていなくて、米あるいは粟くらいしかなかった。日本のマクロビで使っていた豆も、あずき、黒豆、たまに大豆がちょっとくらい。アメリカだと、レンズ豆、ひよこ豆、キドニービーンズ、ピントビーンズなど、私が日本で見たことのないものばかり。オーツ(オート麦)を食べたこともなかったし、玄米と一緒に炊き込むなんてことは日本では試したこともありません。まず野菜や穀物の名前を覚えること、あとは豆の使い方を習う、最初はそんな毎日でした。
ただ、基本の考え方は一緒です。陰陽のバランスをとって調理をする。その土地のものをその季節にいただく。白砂糖、きび糖を使わない。でも、ボストンはメープルシロップがあって、それをどっさり使ったデザートがあったんです。日本では米飴さえも使っちゃいけないと教えられていました。せいぜい、レーズン、りんご、さつまいもくらい。私は甘いものが好きで、ボストンに行ったらメープルシロップたっぷりのチョコレートケーキがあったので、もうこれからはアメリカでやるべきだって真剣に思いました(笑)。
ヨーロッパから来ている人もいっぱいいて、「道夫(久司先生)は俺たちを日本人にするつもりか」なんて言っている人もいました。玄米、海藻、梅干し、味噌を食べろと言っているので、確かにそういうふうに感じるかも。でも、ヨーロッパの人はヨーロッパにある豆で味噌を作ればいいんです。大豆は大体、どこでも採れますしね。実際に今、アメリカではひよこ豆で作られた味噌というのも販売されています。どこに住んでいても、その風土の中でいいものを取り入れていけばいいんです。
癌の患者さんの補助で、2ヶ月ほど香港にいたことがあります。先生のところには、「料理をしてほしい患者がいるから誰か来てほしい」ってしょっちゅう問い合わせがくるんです。その時、私は長女が生後4ヶ月で、アメリカのビザが切れそうで、お金もない。それで、「私、お金もないし、アメリカを出なくちゃいけないんで、行っていいですか?」って先生に申し出たんです
まだ乳飲み子だから自分の子供の料理は作らなくていいから楽なんです。おんぶして、寝たら降ろして、起きたら授乳して。そうやって香港で2ヶ月間みっちりと仕事しました。その後、アメリカに帰ってきて息子がお腹にいる時に次の転機がやってきます。ヨガをやっている方がカリフォルニアにいらっしゃって、その方は自分の家で子供たちに勉強を教えるホーム・スクーリングをしていました。それで、マクロビオティックにもはまっていて、「料理人はいないか?」という話があったんです。私、ある人から「あなたのご主人が30歳になる頃に、彼の人生を変えるような仕事が来るから、必ずやりなさい」って言われていたんですね。それで、私がやりますと、また手を挙げました。「あなたは娘もいるし、旦那さんもいるんじゃないの?」って相手に聞かれて、「そうです」と返事をしたら、「じゃあ、旦那さんも連れていらっしゃい」って、旦那と一緒にお腹も大きい状態で行きました。
そのご家庭のご主人は、『コクーン』という映画のスペシャル・オプティカル·エフェクトでアカデミー賞をとった方でした。西邨は音楽や映像にも関心があって、映画の仕事もしたいと思っていたんです。だから、そのご主人のもとで、奥さんが傾倒していたヨガのビデオの編集を西邨は学びました。。その仕事の経験があって西邨は、下の子供が生まれた頃にはニューヨークに定期的に仕事をしに行くようになったのです。なので、カリフォルニアに行ったことで、彼の人生は変わったわけです。ニューヨークで彼は楽しく仕事をし、私はボストン郊外の山の家に戻って、そこで働き続けました。

そうです。25歳から18年間、マサチューセッツに住んでいたました。プラス2年間は日本に帰って永住権を待っていて、マドンナのところに行ったのは45歳の時です。実は今年の12月で60歳です(笑)。
子育てをしているから、覚えていない部分も結構ありますが、その間に、たくさんの癌の患者さんの面倒を見させていただきました。亡くなった方もいれば、治った方もいる。亡くなられる方のお世話をしていると、どうして手遅れになる前にここに来てくれなかったんだろうと痛感しました。だから、なんとか健康な人に健康なうちにマクロビオティックをやってもらう方法はないのかと、その時に思いました。
大抵はそうですね。でも病気になるって、ひとつだけの理由ではないんです。食事、生活環境、人間関係、経済的なこと、キャリア、気持ちの問題。女性の場合は、自分のことをうまく主張できない、表現できない方が病気になりやすいのではと思います。食事を含む、生き方のバランスが大事なのではないでしょうか。
2001年の5月頃、山の施設にいる時に、「マドンナが子供の料理もできるマクロビオティックの料理人を探している」という話がきたんです。娘が「ママ、それいいじゃない、行ってみたほうがいいよ」と大喜び。で、1週間行くことになったんです。その当時、マドンナと夫のガイ・リッチーは既にマクロビオティックの食事していました。私はマクロビオティックで子育てをして、シュタイナースクールでお弁当を売ったりしていたので、それが認められたようです。
マドンナから「1週間、うちの子供が元気になるもの作ってみて」と言われました。9ヶ月になるマドンナの子供のための食事です。そうしたら3日目から効果が見られ、それからマドンナとガイ・リッチーの食事も作ったら、それも気に入られちゃって。で、結局、10日間いて、また機会があったら声かけてねと、その時はそれで帰ったんです。それで1ヶ月くらいしたらマドンナのアシスタントから電話がかかってきて、「マユミ、ベルリンからツアーに参加しないか」と。子供が6月の10日から夏休みで、その時期なら3ヶ月行けるなあと。子供たちに言ったら娘は大喜び。「やったー、ママ、マドンナのツアーだ!」って。子供たちは玄米だの海藻だの食べて地味に育っていたので、すごく喜んでくれちゃって、賛成してくれました。息子は12歳で夏休みだし、その間は日本に帰しました。
で、3ヶ月、わけのわからないままスタート。まずショックだったのは、ベルリンでは電気で料理しなくちゃいけなかった。ホテルのキッチンを使わせてもらうんですけど、全部電気。マクロビオティックってガスでするのが一番といわれていたから、唖然として。でも、やれと言われたら、やらないと料理人じゃありませんから、なんとかこなしました。初めてマドンナのショーを見て、「へ~、こんな人が私の料理を食べているんだあ」と思ったり(笑)。
ベルリンでは、ホテルのキッチンの一角をマドンナ用に使っていたんですが、そのホテルはマドンナの部屋とキッチンがすごく遠かったんです。いつ食べたいって言うかわからないし、下のキッチンでスタンバッてると、部屋で出してって言われた時に間に合わない。これはどうしようと。冷めたら美味しくないし。だからハウスキーパーが待機していて、私が作ったものを素早く運んでいました。大変な騒ぎでした。お友達がくれば、お友達の分もと言われますし。子供たちのご飯も作っていたので、寝る暇はなかったです。それプラス、「私、寝れないの」ってマドンナに言われて、「私、マッサージなら少しできます」って言っちゃったのが間違いで(笑)、クシ インスティティュートで学ぶマクロビオティックには、基本的な指圧も含まれています。マクロビオティックのシェフというカテゴリーは、まだなかった時代です。他のシェフとは違うという自負があったので頑張ってしまって、私も眠たいけど一生懸命やるわけです。仕方ないですよね、彼女が眠れなかったら次の日ショーができないわけですから。
そうです、なんでも頼めばやってくれると(笑)。ツアーが終わった時に、次は映画の撮影でマルタ島とサルディニア島に行くから来るかって、声かけられたんです。で、「行きます!」って即返事をして。子供たちには事後承諾でした。それで1週間、マサチューセッツに戻ったら、疲労で起きられないんですよ、私。道夫先生に電話して、「体が動きません、どうしたらいいでしょうか?」って聞きました。「何か変な物を食べたの?」「いえ、食べていません」「だったら、玄米のおかゆとワカメをたっぷりとりなさい」と言われて、3食おかゆとワカメのスープで。そうしたら3日間で本当によくなっちゃったんです。それで3日で用意して、マルタ島に行きました。

その時、11月に「マユミ、あなたロンドンに来る?」って言われたんです。アメリカに18年も住んだので、ロンドンも面白そうだなあと思いました。子供には相談じゃなくて、「ママさあ、ロンドンで仕事しようと思うんだけど、どう思う?」と。息子は日本に行かせて、娘は自活できるからということで。で、12月からはロンドン住まい。
冬で必ず毎日雨が降るのですごく落ち込んで。どうして、こんなに天気の悪いところの仕事引き受けちゃったのかしらと思っていました。でも、いい勉強になったのは、こういう気候だからイギリス人は航海に出て、スパイスやお茶を持って帰ってこなくちゃいけないんだ、ということがわかりました。マクロビオティックでもそういう話をすごくします。地産地消であったり、どうして人間が特定の行動をとるかなどを考えるんです。それで、マクロビオティックの良さをまた実感するんですけれど、子供たちにはひどい母親でしたね。「頑張ってね、子供たち。ママ、一生懸命働いてお金作るから」ってほったらかしでしたから。西邨とはもう別居していて、彼も子供達には会っていなかったですね。
ないです。毎食、私が考えた献立です。料理をするのが苦にならないので、マドンナの仕事はぴったりだったんです。料理さえすればよかった。掃除はハウスキーパーがやってくれるのでしなくていい。「ついにやったね、私、お料理だけで生活できるようになった!」って。ちょうど私の子供たちの年齢がマドンナの子供たちと同じ4歳離れている。上が女の子で下が男の子。だから子育てのやり直しをしているような感じもありました。で、マドンナはあんなに忙しい人だから、彼女が自分や子供や旦那さんのご飯のことを気にしなくてもいいようにすることが、私の仕事だと。
子供たちとガイ・リッチーの分と、アシスタントの分まで作っていましたからね。作らなくてもよかったんですけれど、私のマクロビオティックを理解してもらわないと、と思っちゃったのが間違いだったかも(笑)。子供もいるし、ナニー(乳母)もいるし、ロンドンにいる時は毎食、最低10人分は作っていました。体力勝負です。結局、通算10年はやっていたかしら。10年やれば日本では黒帯ですよね。
7年経って、辞めたいと伝えました。マクロビオティックのシェフとして十分やったし、3~4ヶ月経過すれば血液の質が変わる。7年も経てばすべてが中から外まで変わっているはず、と説明しました。
最初の本『小さなキッチンの大きな宇宙』はマドンナの仕事しながら書いたんです。朝7時にキッチンに入らなくちゃいけないので、朝5時に起きて、本を書いていました。とにかくマドンナの仕事をしているうちに1冊出したいと思っていて。別に有名になりたかったわけでなくて、マクロビオティックをどうやって広げたらいいかというのが、長年の課題だったので。
私は学校給食を変えるが一番と思っていました。あるいは有名な人が料理してくれるのがいいと。日本を出た時から、マクロビオティックを世界に広めたいと思っていたので、何かしなくちゃと思っていました。それで、マドンナに辞めさせて欲しいと頼んだら、次のシェフを見つけて来いと言われまして。色々と紹介したけど気に入ってもらえなくて、結局辞めるまでには1年くらいかかりました。
竹を割ったような性格ですね。とても少食で、食べ物に関する節制の仕方は尋常じゃないです。カロリー計算はお互いにまったくしませんでした。とにかく、体が気持ちよく動けるのが一番大切で、それを保っているかどうかが大事なんです。例えば、マドンナの場合は人前に出るので、肌の状態がよくなかったら、それはよくないものを食べているとわかります。自分の一番いい状態というのはどういうことかを知るのが大事で、彼女はそれをよく知っていると思います。会った時からすでに、彼女はマクロビオティックだと思いました。

その後は2009年、10年と少し日本に住みました。2011年に東北の地震があった時、ちょうマドンナのところで私の後任者がお休みをとっていて、私が代わりに行っていたんです。マドンナから、「マユミ、あなた今は帰らない方がいいんじゃないの」と言われ、そしてイタリア人の後任者からは電話がかかってきて「僕、辞めます」と。マドンナはマドンナで「帰ってこなくてもいいわよ、マユミがいるし」ということで、それからまた始まっちゃったんです。2011年から2013年まで、ツアーにも同行しました。やっぱり辞めたいと言った後も、「娘がニューヨークにいるから、娘の面倒を見てちょうだい」と言われたり、ファミリー旅行でスイスにスキーに行く時に、一緒に行ったりしていました。
お互いによく知っているから安心ということですね。余計なことは何も言わないですし。そういう意味では信頼はしてもらっていると思います。こっちも彼女が何が欲しいかわかりますし。今回ベルリンに来る前はロンドンに1ヶ月行っていて、たまたまそのことを知ったマドンナから、「マユミ、パーティーするから手伝いにきて」と連絡がきました。同じ街にいるのがバレると、それならいらっしゃいよ、という感じですね(笑)。
そうですね。あとはエコビレッジというか、マクロビオティック的な考え方でのコミュニティを作りたいと思って動いています。ひとつはもうアラスカにあって、夏の一番いい時期に行ってお手伝いしていますが、今、日本でも淡路島と長崎でそんな動きが出ています。
桜沢如一先生が著書で「日本というのはこんなに素晴らしい食文化をもっていても、いつかは忘れてしまう。海外に残っている日本を逆輸入することになるだろう」というようなことを書いていて、本当にそうなっているんです。アメリカ人がはじめたアメリカン味噌カンパニーがあったり、あるいは海外で初めてマクロビオティックを知って、日本に帰ってからやっている人とか。私としては日本のいいものがなくなる前に、いろいろやらなくてはいけないと思っています。特に子供を持つお母さんたちの意識が変わったら嬉しいなあと思います。
完全なマクロビじゃなくてもいいと思うんです。自分たちが作った野菜を本当に一物全体と思って無駄なく食べる。あるいはそれを循環させていくという人たちが増えたらいいなと思います。アジアはもともと農業をやっている人が多いわけですから、もっといろいろできたらいいなと。で、長生きして、あちこち行ければいいなと思っています。いつかは動けなくなる時がくるわけですから。
今回はベルリンに来ましたけれど、去年はバルセロナ、バレンシア、リスボンでも仕事して、ロンドンの方もよく声をかけてくれます。いろいろな国を回っていると、その土地にあったマクロビオティックってなんだろうって、いつも考えてしまうんです。世界中に通用するものもありますが、もっともっとその土地の人に楽しんでもらえる、あるいは日常生活で気軽に楽しんでもらえるマクロビオティックを提案していきたい。だから声をかけられれば、足代とご飯代とお小遣いが出れば行きます。あとは、相手に任せておけばいいんです。あまり自分でコントロールしようとしてもその通りにはなりませんから。バランスよく生きながら、楽しめるうちは動き続けようと思っています。 (取材・文=浦江由美子 撮影=峯岸進治)
 ベルリンのレストラン『ULA Berlin』で行われたマクロビオティックのディナー。西邨さんの説得力のある解説と共に登場したコースメニューを地元の方々が堪能していました。●撮影協力:ULA Berlin Anklamer Str.8 10115 Berlin Germany http://ula-berlin.de/
ベルリンのレストラン『ULA Berlin』で行われたマクロビオティックのディナー。西邨さんの説得力のある解説と共に登場したコースメニューを地元の方々が堪能していました。●撮影協力:ULA Berlin Anklamer Str.8 10115 Berlin Germany http://ula-berlin.de/
1956年愛知県生まれ。82年に渡米し、マクロビオティックの世界的権威である久司道夫氏の元で学ぶ。83年よりクシ・インスティテュート・ベケット校の設立に参加、同校の料理講師及び料理主任に就任し、癌患者への食事指導なども行う。2001年にマドンナの世界ツアーに同行。マドンナの夫で映画監督のガイ・リッチーのヨーロッパ撮影ロケに参加。その後、マドンナ一家のプライベートシェフとして住み込みで彼らに食事をつくり、ゴア元副大統領、スティング、ブラッド・ピットをはじめ、多くのセレブリティにマクロビオティックの食事を提供。05年12月に初の著書『小さなキッチンの大きな宇宙』を上梓。その後も数々のレシピ本などを出版。『Mayumi’s Kitchen』はアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど広く海外でも親しまれている。現在は企業とのコラボレーションで食品開発をおこなったり、誰でも実践可能な「プチマクロ」を提唱し、世界各都市で講演やイベントなどを積極的に行なっている
●西邨マユミのマクロビオティックを理解するための三冊
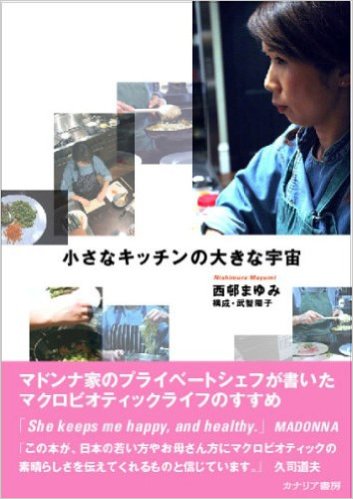
マドンナが来日記者会見で「毎日、日本食しか食べていないわ」とコメントしたことで、一躍有名になった西邨さんの自叙伝であり、マクロビオティック初心者向けの紹介本でもある。「食と生き方」や「子育てと仕事」など、多くの女性が人生の岐路で考えるテーマが、母、料理人、ひとりの女性の視点で綴られている。巻末にハリウッドセレブたちも喜んだマクロビオティックのレシピ付き。(カナリヤ書房)
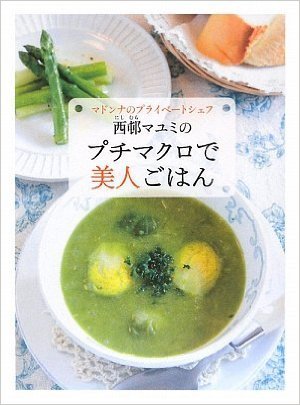
『an・an』の人気連載を再構成かつ大幅な加筆によりまとめた本。「プチマクロ」とは、美と健康を手に入れるために愛されているマクロビオティックを、もっと簡単に楽しく毎日続けられるようにと西邨さんが提唱する食事&生活法。小難しい理論ではなく、ほとんどが身近な食材で作れる料理が紹介されている。すぐにでも始められる10日間朝昼晩ダイエットメニューのレシピ付き。(マガジンハウス)
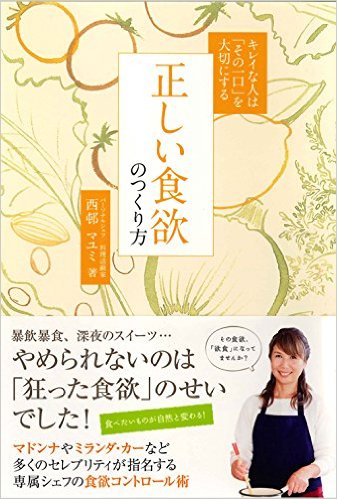
副題は“キレイな人は「その一口」を大切にする”。最近ではミランダ・カーなどにも指名される西邨さんが教える「食欲コントロール術」について。ストレスからくる暴飲暴食や、深夜のスイーツがやめられないなど、食欲のセンサーが壊れてエラーを起こしている状態を正常に整え、「食べたい!」と思うこと自体を変えていくためのハウツー本。食事への考え方が変わる女性必読の一冊。(ワニブックス)

