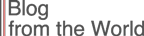「雷が鳴る夜に限って、森のなかをあちこち散歩してまわる不思議なキノコがいる」。南ブルゴーニュのとある田舎町の、そのまた外れにひっそり息づく集落にひとり移り住んだ義理の叔父を、はじめて訪ねたのは10数年前の夏の終わりだった。日が落ちるともうすでに肌寒く、天井の高い石造りの家屋では暖炉に軽く火を入れてちょうどいいような気候。歩き回るキノコの話は、夕食後、甘い食後酒の注がれたグラスと古いパイプという、濃淡の違う飴色の光沢を放つそれぞれを左右の手で愛でながら暖を取りくつろぐ、初老の男性の口からつぶやかれたものだった。

不動産業を営んでいた叔父は、パリのシャンゼリゼに近い瀟洒な邸宅に暮らし、社交は華々しく友人も多かった。けれど、どこか浮世離れして心ここにあらずで、賑やかな席にいても何かの拍子にすとん、と自分だけの世界に埋没してしまうような、独特な翳のある人だった。なんの前触れもなく突然、一切合財から手を引き、少年期のほんの数年を過ごしただけという地に隠遁を決めた時には、もうパリは自分にはうるさ過ぎてかなわないと、自嘲するわけではなく、ただ穏やかに微笑んでいた。
日本では田舎の親戚を訪ねるというような習慣を持たなかった私は、敬愛するこの少々変わり者の叔父の新生活に強く魅了され、時期を変え毎年必ず一度はブルゴーニュに通うようになった。

不動産業に身を置く以前はパリの大学で生物学を教え、専門は菌類学だったという叔父の本棚には、いまだにほこりを被った専門書が並び、そして納屋の奥には奇妙な標本や薬瓶などがごろごろ転がっている。そんな叔父とは庭や周辺で収穫する季節ごとの産物(さくらんぼ、蜂蜜、マルメロ、ラズベリー、りんご、胡桃、等々)を使っては、キッチンであたかも化学の実験でも行うようにしてジャムや焼き菓子をつくって楽しい時を過ごした。

夏の終わりから秋にかけてはキノコの季節で、雨が降った翌日には待ちきれず、朝から長靴を履いて早く森の中に連れていってくれと叔父を急かしたものだった。気まぐれなキノコに出会える確立はとても低く、落胆して戻ることばかりだったけれど、それでも森に向かう時のあのワクワクした感じは格別だった。
村の中心の高台にある教会の敷地内に眠る叔父の墓参りに、この夏はじめて行き、フランスでは今でも土葬がごく一般的なものなのだと知った。この土地の気候と土中の環境で数年が過ぎると、いったい叔父のどこまでが自然に還っているものなのかは想像が及ばず、記憶に残る5年前のあのままの姿で、私の足元に横たわる老人がつと目を覚まして起き上がり、顔や体についた土ぼこりをいとも簡単に払い落とし、ポケットから火のないパイプを取り出してぱくりと咥え、そこでなにか納得したようにこくんとひとつうなづいてから、「ああ、喉が渇いたなあ」と、家のある方角に向かって一歩踏み出しても少しもおかしくないよう気がして、思わずくすりと笑い声をたてた。

親戚の家で夏休みを過ごすといって連れてこられたのに、そこに誰もいない理由はなぜかと、叔父とは行き違いに生まれた子供達に問い詰められ、空の向こうの方を指差しながら“その人は遠くに旅に出てしまっていつ帰るのか分からない”と口ごもると、ひどく生真面目な表情を浮かべ、しばらく互いの目の奥の方で見つめあっていた双子の兄妹が、これはここだけのナイショのはなしだから他の誰にも言っちゃダメだよ、とでもいわんばかりに深刻に密やかに、“あんな遠いところまで行くには、ずいぶんと長い階段を昇らなくちゃいけなかっただろうね” “私たちもいつか、その長い階段を昇ることになるのかな?”と、私の左右の耳元でかわりばんこにささやいた。

フランスの8月は国を挙げての一大ヴァカンス期で、ワイン生産者の多くも休暇中ですが(畑の管理作業はもちろん続きます)、運良くマコネ地区のクレッセ村にあるドメーヌ・ミシェルを訪問することができました。
さて、仏産の貴腐ワインと言えばセミョン種とソーヴィニョン・ブラン種で作られるシャトー・ディケム(Château d’Yquem)が有名です。が、2006年のヴィレ・クレッセの特殊な気候状況から、ドメーヌ・ミシェルの畑では偶発的に広範な貴腐化(ボトリティス・シネレアという菌にブドウが感染して生じます)が起こり、とても珍しいシャルドネ種の貴腐ワインができあがりました。それが、マコン ヴィラージュ エリタージュ2006 (DOMAINE MICHEL MACON VILLAGES HERITAGE 2006)です。

よく熟した果物でできたジャムの濃厚な風味に火打石のような爽やかなミネラルが加わります。甘いワインではありますが、グレープフルーツなど柑橘系の苦味と酸味がしつこさを押さえ、べたつく感じはありません。機会があればぜひ一度味わってみてください。